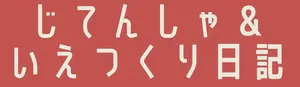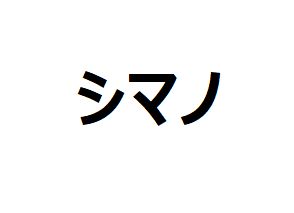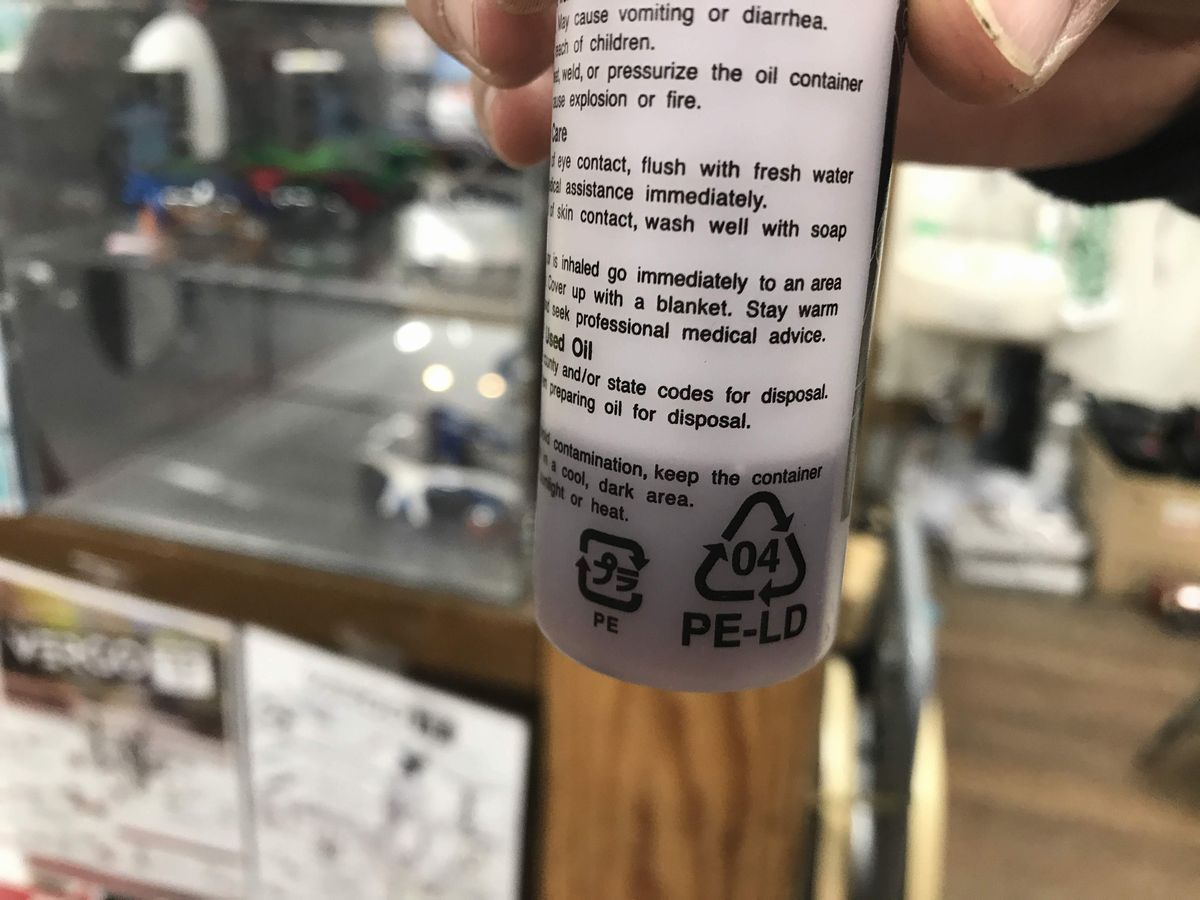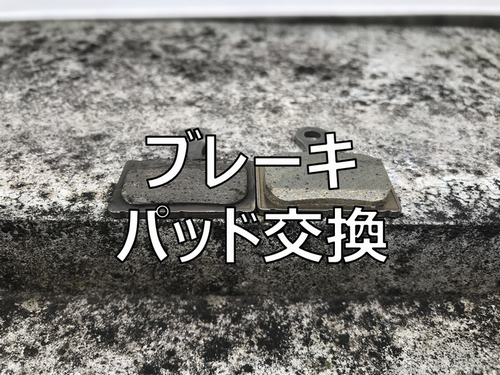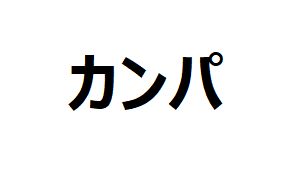『ディスクブレーキにすると、どの程度重くなるの?』気になる重量増の中身を検証してみる
今日もディスクブレーキに対するネガティブ面を調査していきます。今回は『ディスクブレーキにすると、どこがどの位重くなるの?』です。ディスクブレーキを使う/使わない、は別にその人の自由で良いと思います。ただし、
- 重そう
- 輪行でピストン閉じちゃうじゃん
- 逆さにしたらエア噛むんでしょ?
など『興味があるのに、不確かで曖昧な情報だけを元に敬遠してしまう』という不幸な方を少しでも減らしたいと思っています。リムブレーキとディスクブレーキはどちらも一長一短だと思うのですが、大きなメーカーは完全にディスクに舵を切ってしまっています。ハイエンドモデルはディスクブレーキのみのリリースということがもはや普通になってしまいました。既に好みに関わらず、ユーザーとしてはある程度付いていかないといけない状況です。
メーカーとしてはリムブレーキモデルとディスクブレーキモデルの両方を開発・製造し続けるのはあまりにも効率が悪いですから、どちらかにしたいですよね。両方のモデルがそれぞれ従来と同じだけ売れて売上が2倍になるならともかく、市場の大きさは変わらない訳です。従来リムブレーキで10だった売上が、リム:6・ディスク:4みたいになるだけですから。メーカーとしては投資回収出来ませんのでどちらかに絞っていくのだと思いますが、ユーザーとしては迷惑な話です(もちろんメリットもありますが)。
ということで、ディスクブレーキが気になる人のために今回は『ディスクブレーキになると、一体どの程度重くなる(重量増)のか?』を検証してみます。
■ディスクになると重くなる?
ディスクになると重くなるのは本当か
まずディスクブレーキになると、現時点(2020年)では全体としては自転車の重量は重くなります。これは皆さんご存知のことと思います。フォーク先端にキャリパーが移動することで、フォークの強化が必要になるなど、理由はいくつかあります。このような重量増が『どの部分が』『どの程度』なのか?を調べていきます。これを把握することで、軽量化の対策が出来る部分は効率よく対策を行っていきたいですね。

重量増になる部分
リムブレーキモデルと比較すると、重量増になる部分は大きく3つです。『ホイール』『フレーム・フォーク』『コンポ』ですね。ホイールは制動力の発生する場所がリム外周部からハブ付近に移動したため、スポークの本数増加やローターを固定するハブの剛性強化が必要になります。
フレームとフォークは、ディスク用キャリパーの装着される位置をこれまでとは別に強化する必要が出てきてしまったので、その分が重量増となります。特にフォークはフォーククラウンという元々剛性の高い場所にキャリパーが付いてるという合理的な構造だったものが、しなりを主に担っていたフォーク先端にキャリパーが移動してきて剛性も必要になってしまったため、かなりの重量増となります。

コンポは主にSTI(エルゴ)レバーにオイルタンクが増えるため、その重量増です。
ちなみにブレーキキャリパーだけを比較すると、ディスク用キャリパーの方が軽量だったりします。中には軽くなるパーツもあるということですね。
■キャノンデールのUSモデルを元に比較してみる
比較するモデル
検証の方法は、同一モデルのリムブレーキ版/ディスクブレーキ版を比較し、内訳を順に確認してみたいと思います。対象のモデルは、キャノンデールの2019モデル『シナプスカーボン105』と『シナプスカーボン ディスク105』です。シナプスについて、日本にはディスクブレーキのモデルしか輸入されていないのですが、本国のUSサイトを見るとリムブレーキのモデルも併売されています。ホイールとコンポ、フレーム以外は同一構成という非常に分かりやすいモデルです。
まず全体の重量について、リムブレーキ版:8.6kg、ディスクブレーキ版:9.4kg となっており、その差は約800gです。1kg以上の差があると思っていたのですが、意外と差がありません。この800gの内訳がどうなっているのか、確認していきます。
ホイール比較
まずはホイールの比較です。
リムブレーキ版は『フルクラム レーシングスポーツ(Fulcrum Racing Sport)』という完成車用の激重ホイールです。こちらの重量はフルクラム2019カタログによると1,892g。なかなかの重量ですね…。
次にディスク版ですが、こちらは『MADDUX RD2.0』というホイール。この時点で、同じモデルではないので単純な比較が出来ません。
MADDUXのホイールの重量を色々調べましたが、『2kg以上ある』という掲示板の書き込みを見つけられただけでした。このホイールはCAAD12のディスクブレーキ完成車の付属品でもあるため日本にも入ってきているのですが、流石にこのクラスのホイールの重量をわざわざ計測してネットに上げてくれる人は少ないようです。
そこで先日のホイール調査でシマノやマヴィックのモデルを色々調べましたので、それを元に比較すると同じモデルのリムブレーキ版とディスク版では概ね100g~200gの重量差があることが分かります。
例えばMAVICを例にとると、
- キシリウムエリート UST:1,520g
- キシリウムエリート UST ディスク:1,670g
といった具合です。
どちらも同じモデルの完成車付属のホイールですから、ホイールにかける原価は同じレベルだと思います。ここでは仮に、同じモデルのリムブレーキ版とディスクブレーキ版では一般的な重量差『100~200g』の中間を取って150gの重量差があるということにしておきたいと思います。
コンポ比較
次はコンポです。これはシマノなので重量がかなり明らかにされています(残念ながら全てでは無かった)。どちらもR7000系105を使用しています。
まずはリムブレーキモデルから。全部で1,199gです。
| STI | ST-R7000 | 500g |
| FD | FD-R7000-F | 95g |
| RD | RD-R7000-SS | 225g |
| ブレーキ | BR-R7000 | 379g |
| 合計 | 1,199g |
次はディスクブレーキです。合計で1,486g。
※BR-R7070(前後)の重量が分かりませんでした。R9170、R8070との重量差から考えて仮の数値にしてあります。パッドの重量は含まず
| STI | ST-R7020 | 590g |
| FD | FD-R7000-F | 95g |
| RD | RD-R7000-SS | 225g |
| ブレーキ | BR-R7070(F/R) | 310g※ |
| ローター(160mm) | SM-RT70(F/R) | 266g |
| 合計 | 1,486g |
重量差は287gです。結構大きな差、というかローターの分だけ増えているという感じです。コンポの差と言っても、FDやRDは共通なのですから当然ですね。
これ以外にも、厳密にはブレーキのアウター/インナーワイヤー、オイルホース/オイルの重量を比較する必要があります。ですが重量が明らかになっていないこと(使用する長さによっても異なりますし)、オイルホースは両端のジョイント部分が金属製なので重いのですが(ホース自体は軽い)、リムブレーキのアウター/インナーワイヤーも金属製なので意外と重いです。差異があっても数十gな気がするので、ここでは同等の重量ということにしておきたいと思います。
ちなみに、同じ部分をDi2にするとこの重量差は結構縮まって、わずか111g差となります。Di2だとグレードがアルテグラになりますので対等な比較では無いですが、ご参考まで。ローターやキャリパーなどは105グレードのままにしてあります。
| STI | ST-R8070 | 360g |
| FD | FD-R8050 | 132g |
| RD | RD-R8050-SS | 242g |
| ブレーキ | BR-R7070(F/R) | 310g |
| ローター(160mm) | SM-RT70 | 266g |
| 合計 | 1,310g |
フレーム比較
残りがフレームの重量差ということになります。
ホイールの重量差で150g、コンポの重量差で287gでした。これを合計して800gから差し引くと、437g。色々と不確かな部分もあるのですが、フレームとフォークの重量だけでディスクブレーキ版は400g前後が増えているということになります。ちなみにこのノーマルモジュラスカーボンのフレームは、シナプスのアルテグラ版にも使われているものです。

この差を大したことないと考えるかは人それぞれですが、400gは割と大きな差ですよね。
しかし実際に乗ってみた場合、1kgや2kgならともかくフレームの400gの重量差を感じられるのか…?と言われると、私は恐らく分からないと思います…。この中にはあのごついスルーアクスル自体の重量差も入っていますので、単純にフレームに使用されるカーボンの量が400g増えたという事ではありませんが、数値にすると結構な重量増ですね。
■まとめ
シナプス105の場合、全体の重量の差は約800gでした。
正直なところ、これはもうフレームによって全く違うと思いますので、一概には言えません。軽さを追及するなら、もちろんリムブレーキになるでしょう。ただ最近はディスク用フレームの熟成も進んできています(一方でリムブレーキ用フレームは進化が止まっている)ので、数年の内に単なる重量だけではなく、最終的な速さでもディスクブレーキが有利になるのではないでしょうか。トレックのマドンを見たら、あれをリムブレーキでも出せという人はあまりいないでしょう。
今回のシナプスに話を戻しますと、ノーマルモジュラスカーボンを使ったフレームで800gの差なので、ハイエンドのカーボンを使えばその差は更に少なくなります。またホイールとコンポの部分については、お金さえかければ後からいくらでも軽く出来ます。既にディスク用ホイールも1,400g台は珍しくないですし、全体の重量で7kg前半なら容易に作れます。実際に、同じシナプスのHi-MODディスク デュラエースDi2の重量は、完成車で7.2kgです。
ということで、過渡期である2019モデルでは105グレードだとリム⇒ディスクで800g重量が増える。ざっくり言うとフレームが半分の400g、残りがコンポとホイールで半々といった感じ。フレームによる重量増が、大半を占めるということですね。コンポやホイールは後から交換出来ますけども、フレーム買い替えは簡単には出来ませんから、まずは軽量なフレームを選びましょうということか。
ハイエンドのカーボンを使ったフレームにして、コンポはデュラ、ホイールも良いものを使えば800gの差は恐らく300~400g程度までにすることが出来そう。というのがとりあえずの結論です。
これをどう捉えるかは、人によるでしょう。重量至上主義の人からすると受け入れ難いでしょう。しかし『ディスクでエアロ』になったVENGE(7.1kg)やSystemsix(7.6kg)を見ると、多少の重量増があってもトータルでは速そうで、乗りたいという気にさせてくれます。ヒルクラのレースで使うにはさすがに厳しいと思いますが、ブルベやロングライドなら気にならない重量差では無いでしょうか?この程度の重量差であれば、下りや雨でのディスクブレーキのメリットが上回っていると思います。お悩みの方の参考になれば。
最近ようやくこの本を読了しました。非常に参考になる部分が多かったです。トレーニング、機材、補給など内容は多岐に亘ります。